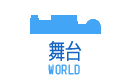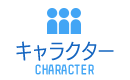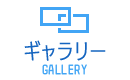トップ > スペシャル > SS > 2018年12月26日SS
12月26日のクリスマス
セミの鳴き声。カンカン照りの太陽。濃いブルーの空。ソフトクリームみたいな入道雲。絵に描いたような夏の光景。
……いや、“ような”じゃないな。実際のところ、絵ではある。周囲の巨大スクリーンに映し出されている景色なんだから。
環境ドームと呼ばれているこの部屋は、最新技術によって擬似的な屋外が再現されており、俺たち唯一の娯楽施設だ。空や青々とした木々を映し出すスクリーンのほか、空調やら太陽光ライトやら、セミのBGMもそうだし、俺の頭上で木漏れ日を作っている木の葉さえ全部人工物。それらのリアルさは実に見事。しかし環境ドームから一歩外へ出れば、そこは暖房の効いた廊下であり、窓の外には灰色の空と、枯れ木で賑わう山々が広がる。現実世界は冬なのだ。
「暑……」
手首に巻かれたビニール製バンドが汗でまとわりつく。入院患者を管理するためのバーコード付きのリストバンド。こうして夏空の下にいると、自分が入院患者であることをつい忘れてしまいそうになるが、間違いなく俺はここに閉じ込められた病人なのだと、このリストバンドが教えてくる。
「暑っちい……」
環境ドーム内の気温や日光は、当然、健康を害しないレベルに設定されてはいるものの、やはり暑いものは暑い。かと言って、特にすることもない病室でどんよりした寒空を眺めながら暇をもてあますのも嫌だった。もうしばらくはここにいたい。
俺は“出前”を取ることにした。
『はい、臨研渋澤……』
「あ、もしもし、渋澤先生。ドームまでアイスと冷たい飲み物持ってきてほしいんすけど。種類はなんでもいいんで」
電話の先は俺の主治医である渋澤先生。なんと俺には先生をパシらせてもいい権利があるのだが、詳細は割愛する。
『……オイ、なめんな』
「特権を行使します」
『チッ』
いかにも苦々しそうな舌打ちのあとすぐに電話は切れた。
と、その途端、環境ドームの扉が開いた。いや、早すぎる。
入ってきたのは渋澤先生ではなかった。患者仲間の三島春輝くんだった。
「……あっ。空歌さん」
「おー、春輝くんも日光浴?」
「……はい。なんだか風が強くて、窓がガタガタゆれてるので、ちょっと嫌だなあって……。あっ、あのっ、ごめんなさい……お邪魔しちゃって……」
「別に謝ることじゃないって。みんなの場所なんだし。ホラ、隣でよければ座んなよ。立ってるとしんどいでしょ」
俺はベンチの端へ座り直した。
「い、いいんですか? すみません。ありがとうございます……」
ものすごく遠慮がちに、そして心底申し訳なさそうに、春輝くんが腰を下ろす。俺の接し方が悪いとかじゃなく、これが春輝くんの性格なのだとはわかっているが、どうにも調子が狂う。ただ、嫌われていないことだけは確かだ。むしろ好かれていると思う。春輝くんの微笑がその証なんじゃないだろうか。形の良い唇、長いまつげ、端麗な曲線を描く横顔。美少年……というより美少女と言ったほうが似合いそうな雰囲気が、取りなしに戸惑う要因でもあるんだよなあ……。俺の隣で、ちょっと楽しそうというか嬉しそうというか。かわいい。そう思っている自分に困るな。
春輝くんを観察する視界の端で、再びドームの扉が開くのが見えた。今度こそ、入ってきたのは白衣の人物だった。
「毎度ぉー、渋澤軒ですー。ご注文のアイスと飲み物お届けに来てやったぞコラ」
渋澤先生は、俺への怒りと不満をみじんも隠さず、威圧的にクーラーボックスを手渡してきた。
「三島が入っていくのが見えたからな、二人分用意してやったぞ」
「マジすかー。ありがとうございまーす。え、でも、このアイス……」
「夕飯入らなくなるだろうが。そのくらいにしとけ」
「まあいいけど……」
俺は袋からアイスを取り出して、半分に割った。そしてスポーツドリンクと一緒にお隣へ差し出した。
「はい、春輝くん。よかったらどうぞ」
「……えっ、えっ?」
俺たちの顔を交互に見つめながら戸惑う春輝くん。確かに渋澤先生をアゴで使う俺という図は不思議に映るだろうな。
「三島。まだここにいるつもりなら、アイスはともかく水分は取っておけ」
渋澤先生の追撃で、ようやく春輝くんはアイスとペットボトルを受け取ってくれた。
俺は小さな瓶型のアイスを吸いながら、べたつく汗以上に俺を苛立たせている事柄を思い起こしていた。――自分で呼び出したくせに――風景とは不釣り合いな白衣を見たら、現実が押し寄せてきて、ついに我慢ができなくなったのだ。
「……なあ、先生。昨日の夕飯にさ、ローストチキンとちっちゃいケーキが出たんだよ」
「ん? ああ、そうだな。食事制限がなくてよかったな」
「俺はそれを見るまでクリスマスだってことを思い出しもしなかった」
「別にいいんじゃないか。俺にとっちゃどうでもいいしな」
「……あ、ぼくも……忘れてました……。ケーキが出るのは珍しいなとは思いましたけど……」
「もおー、春輝くんまで! ここにいると日付もイベントも忘れるくらい世の中と断絶されて関係なくなるって事実こそが悲しいし悔しい! 世間じゃイルミネーションか星空見てイチャついて、イブからひと晩中あんなことやこんなことしてたんだぞ! なのに俺はここに閉じ込められて、今も冬なのにアイス食いながら日焼けしてるなんていう存在しない世界線で生きてるのはどういうこと!?」
「……えっと、ぼくは、クリスマスのお祝いはしたことがないので……あまりわからなくて……」
「だったら、なおさらだよ、春輝くん! 渋澤先生、俺らちょっとだけでも外に出られませんか!? ふもとのショッピングモールが年始までイルミネーション飾ってるらしいから! せめてそれだけでも見に行かせて! なんなら年末カウントダウンの時でもいいから!」
「駄目だ。無理だ。却下。病人だって自覚あんのか。どっちにしろ車で30分以上かかる所にどうやって行くつもりなんだ」
「そりゃ先生が車で」
「却下」
「キャンドル病って言ったって、俺も春輝くんもなんともなってない。自覚なんかあるわけないだろ……! いつまでこんなとこ閉じ込められてなきゃいけないんだよ!」
「そ、空歌さん……。あの、渋澤先生……ぼくは体力がないので、きっとご迷惑おかけすると思うのでいいですから……空歌さんだけでもなんとか外出許可は降りませんか……?」
春輝くん、天使か……。
「悪いが三島、これは俺の許可がどうこうという話じゃない。キャンドル病が新感染症として指定され、隔離という措置が定められている以上、法律の問題なんだよ。もし俺が免停か免剥にでもなったら誰がお前らを治すんだ」
「…………すみません……」
くそ。わかってはいたけどさあ……。ダメモトで言ってみただけだけどさあ……。
「はあ。俺がかわいそうだ……」
「そこは三島がかわいそうだろ。義務も果たさず権利だけ行使してるお前はかわいそうじゃないしかわいげもない」
「ひどい」
「あ、あの、空歌さんっ、ぼくがかわいそうがりますからっ……ああ、いえ、あのっ、そう言うのはなにか変ですね……! ぼく、イルミネーションとか見たことなくて、クリスマスのお祝いも参加したことがないので、よくわからなくて……本当の意味で空歌さんの気持ちはわかってないかもしれないんですけど……すみません……。で、でも、ぼくは空歌さんと一緒に過ごせてうれしいですっ。あの、年末か年始は一緒にお祝いしませんか? お友達とそういうことするの初めてで、なにをするのかよくわかっていなくて、ぼくとじゃつまらないかもしれないですけど……」
「……ううん、そんなことない。すげえうれしいよ。ありがとう。カウントダウンしような。春輝くんは教会の絵にいそうな天使っぽくて癒しになるなあ。今クリスマス感ちょっと味わえてるかも」
「え、はいっ、えっ……!?」
「……佐々木、理解したなら俺は戻るぞ。暑い。お前らもほどほどにして部屋に帰れよ。三島はきちんと水分を取りなさい」
渋澤先生は事務的に言い放って環境ドームから出て行った。扉が閉まると同時に、俺は春輝くんに頭を下げた。
「ごめん。春輝くんだって、ほかの人だって同じ立場なのについ愚痴った。言ってもしょうがないのはわかってるんだけど……」
「いえ、謝らないでください……! ぼくのほうこそ、行事にうとくてすみません……」
当たり前の青春すら楽しんで来られなかったであろう春輝くんの言葉が胸に痛い。本当に、どうして俺たちがこんな目に遭わなきゃいけないんだろうな。きれいな青い空が、急に白々しく思えた。
昨日のチキンとケーキが幻だったかのように、夕食はもちろん普通のメニューだった。そりゃそうだ。今日はなんの日でもない。
食事も検温も終わり、もうなにもすることがない。あとは眠るだけ。日々が過ぎるのが、遅くて、早い。あまりにも空しすぎて、いっそ病気が悪くなってなんらかの症状が出れば刺激的な毎日を送ることができるんじゃないか、などとタチの悪い考えさえ思い浮かぶ。外の世界が恋しい。
消灯まであと一時間以上もある。さっきから何度も時計ばかり見ている。
そこへ不意にノックの音がした。
「はーい?」
「そうくん、まだ起きてた!」
弾むように飛び込んできたのは、患者最年長の安田さんだった。妙な勢いのよさには、あきらかに非日常が香っている。
「ど、どうしたんですか」
「いいから、来てみて!」
唐突な来訪に面食らったのも束の間、安田さんの明るい表情から、いい意味でただ事じゃないと察した俺の胸中はすぐにワクワク感で満たされた。
「なになに。すぐ行く」ベッドから跳ね起きる。
「ああ、待って。コートを羽織って、あったかい服装でね。サンダルじゃなくて靴を履いて」
言われるがままにそうする。まさか、外出できるのか? いや、そんな簡単に事が進むわけがない。だけど安田さんの格好も確かに外出するような厚着だ。わけがわからない。が、とにかく従った。
廊下へ出ると、同じようにコート姿の春輝くんがそこにいた。
「え、マジでなに?」
安田さんは俺の質問に答えず歩を進める。
「よし、二人とも行こうか」
「あ、あの……安田さん……本当に、一体……?」
「ふふ。言ったらつまらないじゃない。お楽しみ」
安田さんの引率はほんの数メートルで終わった。立ち止まったのは環境ドームの扉の前だ。
「ちょっと待って! ドームいま夏気温! この格好じゃ暑いって!」
「いいからいいから」
この中がどうなっているかなんとなく予測できているのと、でもまさかなという思いが交互に湧く。
環境ドームに入れば答えはすぐに出た。
「わあ……すごい……!」
春輝くんが声を上げた。俺は言葉もなく見入った。色とりどりの光と、それを受けてキラキラと舞う雪。数時間前に木漏れ日を作っていた樹木は、今は冬の枯れ木と化し、代わりに点滅する絢爛な電飾を纏っていた。周囲の景色はまぶしいくらいのビル群。俺は一瞬だけ本当に街中に立っているのだと錯覚した。だって人工の木ができることは葉っぱを出したり引っ込めたりだけのはずだ。確かに環境ドームは日光も雨も雪も本物が出るし、周りの景色は映像だから自由に変えられるのもわかる。だけど電飾はそうもいかない。環境ドームではあり得ない幻想的な光景が広がっているのだ。
「これで我慢しろ」
声がして、ようやく真横に渋澤先生がいたことに気付いた。
「一般病棟のデカいクリスマスツリーが片付けられたからな。電飾をこっちに回してもらった。ったく……二度とやらん」
「……先生がこれやってくれたんすか」
「特権による“外に出てイルミネーションが見たい”というお前の希望を範囲内で叶えるにはこれが限度だ」
「いや、充分っす。ありがとうございます」
イルミネーションに負けないくらいにキラキラとした表情の春輝くん。楽しそうな安田さん。そして……
「皆川、遅い。ドームの開放時間が終わっちまうだろ。俺の苦労を無駄にするな」
渋澤先生が声をかけた先に、皆川さんの姿があった。いつも無愛想で冷たくて全然しゃべってくれないくせに、渋澤先生の言うことなら素直に聞くのか……。
「興味ないんですけどね。先生がそこまで言うならと、仕方なしにですから」
そう答えながらも、遠巻きにツリーを見上げる顔はまんざらでもなさそうだ。きちんと厚着して来てるあたり、すぐに戻る気はないようだし。
「空歌さん! ぼく、こんなの見たの初めてです……! すごい……きれい……」
控えめにはしゃぐ春輝くんを見ていると、特権があってよかったとますます思う。俺の勝手なわがままが、結果的にみんなのためにもなった。先生には苦労をかけて申し訳ないけど、これはこれで満足だ。
なんとはなしに安田さんと目が合い、お互い春輝くんへ微笑ましい目線を向けていたことに気付く。そしてまた目を合わせて軽く笑った。
「これって、よくわからないけど、そうくんのおかげなんだよね?」
「うーん。いや、やっぱり結局は先生のおかげかなあ……」
「そっかあ。きれいだねえ、そうくん。一日遅れだけどこれはホワイトクリスマスだねー」
「あ、俺も同じこと思ってた」
「そうくんも、春輝くんも、学くんも、寒くはないかな? 冬設定でも雪が降るなんてめったにないからねー」
「うん、平気。地面に雪が積もってないから、そんなに気温低くないっぽいし」
「あ、ぼ、ぼくも、大丈夫ですっ……」
……皆川さんだけ返事がない。無視かよ。まあいいか……。普段まったくとりつく島もない感じの皆川さんが素直にここにいてツリーを眺めてるんだ。それだけでも大したもんだろ。
たまにはこんな日があってもいい。歩く細菌兵器みたいな扱いされて隔離されて閉じ込められた俺たちだけど、自分の境遇なんて忘れて、普通に街のイルミネーションを眺めている、そんな思いにひたる瞬間があったっていいじゃないか。
今日12月26日のクリスマスのことを、俺はずっと忘れないだろう。